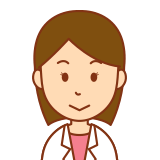
保育の方針として「自由保育」と「一斉保育」がありますが、職員にとって負担が少なく「楽」なのはどちらですか?
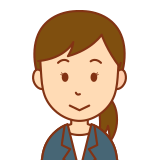
職員にとって一概にどちらが楽とは言えませんが、事務作業や準備の「量」を減らしたいなら「一斉保育」、子どもの対応や臨機応変な動きの「質」の負担を減らしたいなら「自由保育」のほうが精神的な負担が少ないと感じる方が多いです。
ただし、自由保育は高度な専門性が求められ、楽になるには職員間の連携が必須です。
事務負担が少ないのは「一斉保育」だが、精神的負担は増大
従来の保育園で多く採用されてきた一斉保育は、あらかじめ組まれたカリキュラムや時間割に沿って活動を進めるため、活動内容の計画自体は立てやすいという特徴があります。これにより、指導案や日誌などの書類作成の「型」が決まりやすく、事務作業の量的な負担は自由保育より少ないと感じる保育士さんが多いでしょう。
保育現場の状況として、一斉保育は「皆で同じことをする」ため、職員は子どもたちの行動を予測しやすく、集団を統率することに集中できます。活動の成果が目に見えやすいため、保護者や園長などからの評価を得やすいという側面もあります。
しかし、意外な視点として、一斉保育は子どもたちの「やりたい」という意欲を抑えつける場面が多くなり、活動への意欲が低い子への声かけや、集中力を維持させるための精神的な労力が非常に大きくなります。子どもを抑えつけることへの自己嫌悪から、ストレスを感じやすいというデメリットがあります。
職員にとっての「楽さ」とは、作業の効率だけでなく、精神的な消耗が少ないことも重要です。一斉保育は事務作業の量は少なくても、子どもたちの意欲を引き出すための精神的な消耗は大きくなりがちです。
自由保育は「準備と観察」がカギ!負担の質が変わる
自由保育は、子どもたちの主体的な興味・関心に基づいた活動を尊重するため、一斉保育のように時間で区切られた活動はほとんどありません。これにより、子どもたちの動きに合わせて臨機応変に対応するスキルが求められ、一見すると「楽ではない」と感じるかもしれません。
自由保育における職員の仕事の質は、「活動を導く」ことから「子どもの活動を深く観察し、環境を整える」ことに変わります。例えば、子どもが積木遊びに夢中なら、積木の種類を増やしたり、遊びが深まるような声かけをしたりと、事前準備と環境構成に多くの時間がかかります。
待遇・働きがいという視点で見ると、自由保育を実践する園は、保育士の専門性を重視する傾向が強く、日々の保育を深く考察できるため、仕事の質的な満足度は高いと感じやすいでしょう。一方で、その質の高さゆえに、自由遊び中の記録や、子どもの発達に関する考察の事務作業は増える場合があります。
自由保育の「楽さ」は、子どもが自ら活動を選ぶことで、保育士が子どもたちを管理するストレスから解放される点にあります。ただし、この「楽」な状況を作るためには、職員間での高度な情報共有と連携が不可欠です。
経験やライフステージで感じる「楽さ」は異なる
職員が「楽」だと感じる保育形態は、個人の経験やライフステージによって大きく異なります。例えば、経験豊富なベテラン保育士は、長年の勘と技術で集団を統率しやすいため、一斉保育を効率的にこなせると感じるかもしれません。
一方、若手やブランク明けの保育士は、完璧な計画の元に進む一斉保育よりも、子どもたちの様子を見ながら柔軟に対応できる自由保育のほうが、プレッシャーが少なく精神的に楽だと感じる傾向があります。
個別事情として、子育て中の保育士さんは、保育経験から子どもの行動の予測がつきやすいため、一斉保育でも自由保育でも対応しやすいかもしれません。しかし、短時間勤務の場合は、途中参加しやすい自由保育のサポート役のほうが、負担が少ないと感じるでしょう。
結論として、「計画立てて動くのが得意な人」は一斉保育が楽に感じやすく、「子どもの変化に合わせ柔軟に対応するのが得意な人」は自由保育が楽に感じやすいという、得意・不得意に基づく違いがあります。
理想の保育と「職員の心のゆとり」の両立を目指して
どちらの保育形態が「楽か」という問いは、裏を返せば、「どのようにすれば保育士が疲弊せずに、質の高い保育を提供できるか」という切実な問題に繋がっています。どちらか一方に偏るのではなく、それぞれの良いところを取り入れた保育を目指すことが理想です。
もし今の園の保育方針に疲れを感じているなら、それはあなたが「子どもたちのために」という高い意識を持っている証拠です。その負担を減らすためには、園全体の業務改善(ICT導入など)や、職員間の協力体制の見直しが不可欠です。
不安を抱え込まず、園長や主任に「どのようにすれば効率よく、子どもたちの主体性を尊重できるか」を建設的に提案してみましょう。職員の心のゆとりこそが、子どもたちへの優しい関わりに繋がり、結果として質の高い保育を実現させます。
あなたの持つ「子ども中心の保育をしたい」という理想と、現実の「働きやすさ」を両立させるために、今一度、ご自身の得意な働き方を見つめ直し、前向きに環境を変える一歩を踏み出しましょう。

