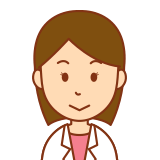
多くの保育園で掲げられる「子ども中心」の保育方針は、実際の現場ではどのような実態や特徴がありますか?
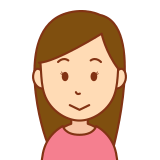
「子ども中心」の保育とは、単に子どもを自由に遊ばせるのではなく、子どもの主体的な活動や興味・関心を最優先し、大人はその環境を整えることを重視する保育です。
実態として、大人の「教える」から「見守り、支える」への意識改革が必須であり、自由遊びの時間の確保や、子どもが選べる多様なコーナー設定などが特徴として見られます。
「大人の都合」からの脱却!主体性を尊重する環境づくり
「子ども中心」という言葉は理想的ですが、保育現場には集団生活という側面があるため、実際には「時間割」や「行事の準備」など、大人の都合や効率が優先されてしまいがちな背景があります。子ども中心を掲げる園は、まずこの「大人の都合」から意識的に脱却する努力が求められます。
従来の保育は、一斉活動や指示による活動が中心でしたが、子ども中心の保育では、子どもが「何をしたいか」「どうしたいか」という内発的な動機を尊重します。そのため、保育士は指示役ではなく、子どもたちの活動を深めるための環境設定や援助(ファシリテーション)が主な役割となります。
意外な点として、一見「自由」に見えるこの保育は、実は高度な専門性が求められます。子どもが本当にやりたいことを見つけられるよう、様々な素材や道具を用意し、子ども同士の関わりを見守るという、綿密な計画と観察に基づいているからです。
この方針の実践は、子どもたちにとって、自己肯定感を育み、自ら考え、行動する力(非認知能力)を高めるという大きなメリットをもたらします。保育士は、子どもたちの「やりたい!」を全力で応援するサポーターへと役割を変化させていきます。
職員の協調性と専門性が問われる!現場の負荷とやりがい
「子ども中心」の保育を実践するには、保育士個人のスキルだけでなく、職員間の高い協調性が求められます。子どもたちの活動が予測不能であるため、誰がどのタイミングでどの援助に入るかなど、チーム全体で柔軟に対応する体制が必要となります。
その背景として、自由な活動が増えることで、子どもたちの個々の関わりを記録したり、援助の内容を職員間で共有したりする時間が増え、担任制の保育よりも記録や情報共有の業務が増えることがあります。また、子どもの活動を深めるための環境構成に時間と労力がかかるのも特徴です。
しかし、待遇や働きがいという視点で見ると、この方針は保育士の専門性を大いに高める機会になります。子どもの行動の「なぜ?」を深く考え、環境や声かけを工夫する探求的な姿勢が身につくため、高いモチベーションで仕事に取り組めるという大きなメリットがあります。
業務負荷は増えるかもしれませんが、「子どもたちが自発的に成長していく姿」を目の当たりにする喜びは格別です。この方針を掲げる園は、保育士の学びを重視する傾向にあるため、研修制度が充実しているかを確認することも大切です。
保護者との意識のすり合わせと個別支援の充実
「子ども中心」の保育園では、保護者との意識のすり合わせが特に重要になります。保護者の中には、「毎日何かを教えてほしい」「お遊戯などの目に見える成果がほしい」と考える方もいるため、保育の狙いを丁寧に伝える必要があります。
特に、自由遊びの時間が長いことに対して、「何を学んでいるのだろうか?」と不安を感じる保護者も少なくありません。園側は、子どもたちの遊びが「学び」につながっている具体的な記録やエピソードを、積極的に共有するコミュニケーションが不可欠となります。
この保育方針は、子どもの個性や発達のスピードを尊重するため、個別支援の充実につながります。集団からはみ出してしまう子や、特定のことに強いこだわりを持つ子に対しても、その子のペースに合わせた環境や援助を提供することが容易になります。
ライフステージの変化に伴い、保護者の価値観は多様化しています。子ども中心の保育は、保護者も子どもの主体性を尊重する姿勢を持つことにつながり、家庭と園が連携して、子どもの健やかな成長を支えるという意識を深める効果が期待できます。
理想と現実のギャップを埋め、子どもと共にある保育へ
「子ども中心」は、保育士にとって「理想の保育」の姿である一方、人手不足や行政対応など、様々な現実的な課題の中で、その方針を貫くことの難しさを感じる場面もあるかもしれません。理想と現実のギャップに悩むこともあるでしょう。
もし、あなたの園でこの方針がうまく機能していないと感じたら、それは個人の責任ではなく、「職員全体で子ども中心とは何か」を深く議論する機会が不足しているサインかもしれません。小さな活動一つから、子どもたちの「やりたい」をどうサポートできるか、同僚と話し合ってみましょう。
大切なのは、形式的な「子ども中心」の看板を掲げることではなく、日々の保育の中で、どれだけ子どもの声に耳を傾けられているかという実態です。子どもたちが生き生きと活動しているか、その笑顔が何よりも方針が成功している証拠となります。
あなたの保育への情熱と、子どもたちの主体的な力を信じる気持ちが、園の保育をより良いものに変えていく力となります。自信を持って、子どもたちと共に遊び、共に学び合う、心豊かな保育を追求していきましょう。

